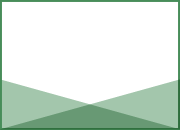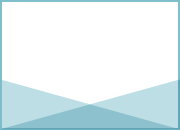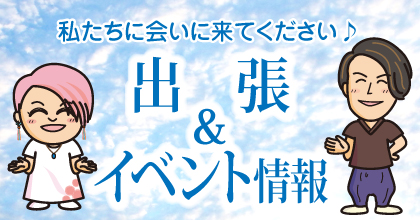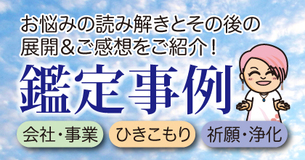仕事を辞めて実家に戻った息子
鑑定内容
『仕事を辞めて実家に戻った息子のひきこもり』についてのご相談
息子が仕事を辞めて実家に戻ってきた。
仕事を探す様子もなく、話しかけると怒鳴り、機嫌を損ねると暴れるようになった。
- ご相談者様 母親 78歳
- ご相談対象者 息子 52歳
ご相談内容の詳細
息子が仕事を辞めて家に帰ってきましたが、一向に仕事を探す訳でもなく、家から一歩も出ず、話しかけたら怒鳴り、用事を頼んでも動こうとせず、少しでも機嫌を損ねると暴れます。 どうしたらまともになりますか? 考えていることもわからず、この先ずっとこのままなのか?
私も高齢でいついなくなるかわからないのに、この子は自分が居なくなっても生きていけるか心配です。

自分も高齢になり支えるにも限度がある不安の中、何もしない息子さんのことを考えるといてもたってもいられない状況は耐え難い気持ちが伝わってきました。
リーディングの前に、ご相談者様に何点か質問させていただきました。
息子さんは結婚もせず転職を何回もし、転職する度に家に帰ってくるを繰り返していたそうです。
その度に、仕事を探すよう促したり知り合いの口利きで職の斡旋をしたりと、親の出来ることを都度提供し自立出来るよう促されてきました。
相談者様から見た息子さんは、
- 仕事はまじめにこなす。
- 順調に生活をしている間は電話もしてこない息子だが、こちらから連絡すると返事は返ってくる。
- たまにフラッと帰ってくることはあっても、長居することなくまた自宅に帰る。
- 親の側にいることは少なく、つい最近も本州で仕事をしていて安定してきたと安心していたところ、何の連絡もなく帰ってきて一向に自宅に戻る気配が無いので話を聞いたところ、実は仕事を辞めたと言ってきた。
- 1ヶ月が経ち、仕事をするよう促したら急に怒鳴り散らし暴れるようになった。
- 性格は温厚で気持ちの優しい子。
- 言葉数は少ないが頼んだらなんでも手伝ってくれた子なのに、今は一切何もしようとしない。
- 何が起きているのかわからない。
- 病気かとも思い病院に連れて行ったら軽いウツと診断され薬も出たが、薬を飲むことも無く一日中TVを見て過ごしている。
読み解き
上記の内容を踏まえ、52歳の息子さんのリーディングをしてみました。
相談者様の仰るように、性格は温厚で人当たりも良く真面目。
嫌なことがあっても否定せず、自分が我慢していたら事を荒立てる必要も無く平和に暮らせると、自らへ言い聞かせて心の負担を軽減させる。
不器用なりに努力はするものの、うまくいかないことがあると投げ出す傾向あり。
人を頼らずなんでも自分でやる性格で、思い通りにいかないと全てが嫌になり後先考えずに行動する。
という内容が伺えました。
そして、今の心境は、
- 全てに疲れた。
- 何をやってもつまらない。
- 今まで真面目に生きてきて、何一つ身になっていることがない。
- こうなった原因は全て親にある。
- 本来あるべきものが無い。
- 結婚も家族も友人もいないのは、親が自分の世話をちゃんとしなかったから。
- 自分は不幸だ。
という思いが視えてきました。
内容からわかる、この方の魂の課題
このような内容からわかる、この方の 魂の課題は『手放す』です。
上手くいかないことや思い通りにいかないことを全て親のせいにすることで、果たせなかった思いには欲が入り混じり行き過ぎるとエゴに変わります。
欲がエゴに変わり、自己都合の考え方で生きづらい自分になってしまったのも「不幸な原因は親」と人のせいにして、自らがそうしたということに気づき、原因となる欲とエゴを手放すことが課題です。
また、相談者様の課題も『手放す』です。
子供のことが心配で相手が望んでもいないのに、口を出し手をかけ、『子供だから』という意識が息子さんを甘やかし彼に考える余地を与えなかった。
人しての意識で対応することで厳しいことを言うことになりますが、自立心を芽生えさせる機会はいくらでもあったと思われます。
親として子を『人として』の対応で、自ら子離れする『手放すこと』をしなかった結果が今でしょう。
よくよく話を聞くと、 お母様である相談者様は、息子さん可愛さと心配で逐一彼の現状を聞き、把握することで自分への安心を得ていたようです。
また、彼に彼女がいることを知った時も、息子の幸せを願う前に彼女に大切な息子を取られるという焦りと恐怖から、息子への執着心をあらわにしていたことも判明しました。
全てお母様が原因ではありませんが、親に心配かけたく無い息子の思いやりと息子を不幸にしたくない親心が、望んでいない不幸を呼び寄せる結果になりました。
思いやりや愛情が深いと互いの幸せが「重たい槍」になり、その負担が愛憎に変わったようです。
その後の変化

既に取り返しはつかないけど、自分の出来ることは息子の幸せを願うことなので、彼と今まで本音で話してこなかった自分を反省し、大人としての彼という「一人の人」としての対応をすることで、自分が家にいない間に出来ることをやってくれるようになってきたそうです。 また、文句は言っても暴れることも少なくなり、母親としてではなく「一人の老人」として扱うことも見えてきたので、否定せず受け入れているとのこと。
自分のやりたいことが出来ている間は笑顔も見えてきたので、このまま継続していこうと思うとのことでした。
★お客様からの感想

手放すの意味は未だわからないけど、優しかった息子がその影も形も無くなったのは全て自分の責任であり、親として良かれと思ったことが、彼の人生を不意にされた憎しみとなり今自分に向けられているのはわかった。
息子の笑顔が少しでも長く見ることが出来るのが、今の自分の生きがいになりつつあります。
- ご相談者様 母親 78歳
まとめ
 自分がどうなりたいかでどうありたいかが大切。
自分がどうなりたいかでどうありたいかが大切。
人のためと思うことも実は自分のためであったりします。
押し付けと思っていなくても、大切にしたいからこそ無理強いしていることも多いものです。
相手の言葉や態度に変化を感じた時。
それも自分が望んでいないことがあり、心が苦しくなったり辛くなった時は、相手も同じなんだと気づくことで本当の思いやりで接することが出来ます。
人の心は気遣いでどうにかなるものでは無く、自分がどうなりたいかでどうありたいかが大切です。